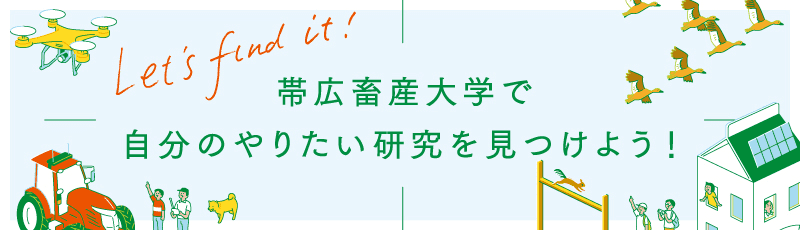第77回畜産学部、第59回大学院畜産学研究科並びに第66回別科酪農専修の入学式が、4月4日(金)午前10時から講堂において、挙行されました。
式典では、畜産学部262名(編入学生8名を含む)、大学院畜産学研究科64名、別科酪農専修15名の入学が許可されました。
次いで長澤学長から告示が述べられたのち、長谷山 彰理事長からの祝辞映像が放映されました。
その後、入学者を代表して共同獣医学課程の常住 小春(つねずみ こはる)さんから「学業に励み、学生の本分を尽くすことを誓います。」と宣誓が行われました。
最後に、来賓・教職員の紹介があり、マンドリンサークルによる帯広畜産大学逍遥歌の演奏ののち、式が終了しました。
学長告辞
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。帯広畜産大学を代表して、お祝いを申し上げます。
皆さんは、これまで異なる環境で育ち、一人ひとり違った才能を持ち、多くは生まれ育った土地を離れ、今ここに、進む道を同じくした仲間たちと共にいます。
皆さん自身が、これまで努力と研鑽を重ねた結果、本学に入学するという目標を達成されたことに対して、心から敬意を表します。また、その志を支えてくださった、ご家族並びに関係者の方々に対し、心よりお慶び申し上げます。
皆さんが本学入学を目指した動機は、様々なことと思います。オープンキャンパスが動機となった方も多いでしょう。本学の教育研究内容、あるいは本学が取り組んでいる様々なプログラムに興味を持った方もいると思います。また、雄大な北海道の自然環境の中で、学生生活を送るのが動機となった方もいると思います。
昨年、新たな国立公園として「日高山脈襟裳十勝国立公園」が環境省に承認されました。南北140キロにわたる手つかずの自然環境が数多く残る、国内最大の国立公園です。北には、北海道の最高峰である旭岳、活火山の十勝岳を含む「大雪山国立公園」、東にはマリモで有名は阿寒湖、日本一透明度の高い神秘の湖の摩周湖がある「阿寒摩周国立公園」があります。それらに囲まれた十勝平野は、関東平野、石狩平野に次いで3番目に広く、中心を流れる十勝川は太平洋沿岸の豊かな漁場に繋がっています。地平線を望むことのできる雄大な自然環境は、北海道の中でも特に素晴らしいものです。
今から約140年前の1885年(明治18年)に、民間の移民団である晩成社を率いた依田勉三は、北海道全域を調査した結果、広大な十勝平野が、農業・酪農に適した土地であると確信して、開拓を始めました。原野から農地への転換は困難を極め、時代の先を行く酪農事業は挫折を繰り返しました。結局、晩成社の事業は失敗に終わりましたが、十勝における産業基盤と開拓者精神の形成に大きく寄与しました。今なお、依田勉三の思いは、精神的源流として十勝に生き続けています。
127年前(明治31年)には、昨年発行された1万円札に、その肖像が刻まれている、「近代日本経済の父」である渋沢栄一が十勝に注目し、畑作や酪農業を手掛ける「十勝開拓合資会社」を創設しました。
渋沢栄一の著書には、「従来接した景色の中で、最も雄大で、心を打たれたのは、狩勝峠から見下ろした十勝平野の風景である」と記しています。さらに、「十勝は実に雄大であり、コセコセしたところがなく、米国あたりの大陸にある風景のごとくであり、日本の景色とは思えぬほどである。」とあります。
先人たちの苦労により、幾多の苦難や試練を乗り越え、今日では、十勝は、食料自給率1345%を誇る、我が国有数の農業・酪農の中心地として発展しています。
さて、本学は、1941年(昭和16年)に、文部省が日本の中で、十勝帯広が最も適した場所と認定して、我が国で初の官立高等獣医学校として創設し、今年で84年目を迎えます。これまで、数々の教育改革を経て、現在、畜産学部には、畜産科学課程と共同獣医学課程、および地域農業の中核的リーダーを養成することを目的とした別科(酪農専修)があり、より先端的な学習と高度な技術習得を目的とした大学院畜産学研究科に、畜産科学専攻博士前期課程及び博士後期課程、並びに獣医学専攻博士課程が設置されています。
また、2022年(令和4年)4月には、帯広畜産大学、小樽商科大学、北見工業大学の3大学が経営統合し、国立大学法人北海道国立大学機構となりました。農商工連携により、北海道経済・産業の発展と国際社会の繁栄並びに、SDGsに示された持続可能な社会の実現に貢献することを目標にしています。
農学の歴史は古く、人類の歴史とともに歩んできました。当初、農学は人類の生活の糧を担う学問でしたが、現在では、食料生産だけではなく、食品加工や流通、食の安全安心といった分野も対象としています。
また、農学は食料や資源として生物を扱うことから、生命に関わる基礎科学も重要な要素となります。さらに、生物と環境が対象となることから、環境問題においても、その解決には農学の知識と実践力が必要となっています。
農学は、食料や生活資材、生命、環境を対象とし、自然と社会すべてに関わる総合科学です。
今日、私たちを取り巻く環境は、誠に厳しいものがあります。本年2月4日に帯広では、観測史上最大となる一晩で124cmの積雪がありました。気候変動にともなう自然災害は、世界中で、後を絶ちません。また、人口問題に関して、日本では少子高齢化による生産人口の減少や地方創生が課題となる一方で、世界の人口は増加し続けています。人口の増加に伴い、エネルギーや食糧が必要となります。その結果、森林の減少、砂漠化が進み、環境破壊が問題となっています。
日本の食料生産の中心地として、「生産から消費まで」一貫した環境が揃う十勝に位置する本学は、生命、食料、環境をテーマに、農学、畜産科学、獣医学に関する教育研究を推進する、我が国唯一の国立農学系単科大学です。
本学のミッションは、「知の創造と実践によって実学の学風を発展させ、『食を支え、くらしを守る』人材の育成を通じて、地域及び国際社会に貢献すること。」です。
これから始まる学生生活において、自然と社会すべてに関わる総合科学である農学を学び、直面する社会課題を解決するための素養を育んでください。
皆さんには学業の他に、クラブ活動やボランティア活動などにも積極的に参加していただきたいと思います。十勝の開拓の歴史を知り、地域の多様な人々の考えや文化に触れることも大切です。そうした学業以外のアクティブな時間を送ることによって、多様性を受け入れる人間性が育まれ、大学生活は豊かになります。新しい学びあいのコミュニティは、大学の内外に存在しています。
終わりに、新入生の皆さんが、それぞれの目標に向かって、志を高く持ち、悔いのない学生生活を過ごし、生命・食料・環境分野の専門知識、社会に通用する教養、社会情勢の変化や諸課題に対応可能な応用力やコミュニケーション能力を身につけ、大きく成長されることを祈念し、告示といたします。
令和7年4月4日
帯広畜産大学長
長澤 秀行