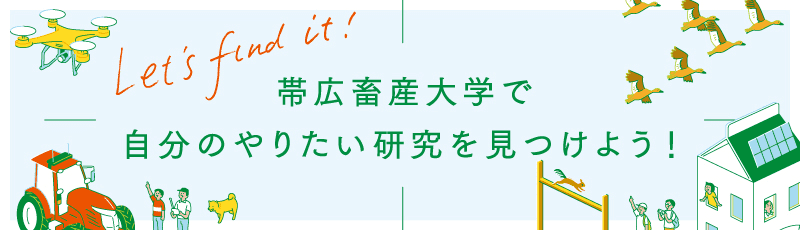もし,ハラスメントにあったら
基本的な心構え
- ハラスメントを無視したり,受け流したりしているだけでは必ずしも状況は改善されないということをまず認識することが大切です。
- ハラスメントに対する行動をためらわないことが大切です「トラブルメーカー。というレッテルを貼られたくない「恥ずかしい」等と考えがちですが,被害を深刻なものにしないために,勇気を出して行動することが求められます。
- ハラスメントに対しては毅然とした態度をとり,はっきりと自分の意思を相手に伝えることが重要です。
- 同僚や友人等身近な信頼できる人に相談することが大切です。そこで解決することが困難な場合には,学内または学外の相談機関に相談する方法を考えてください。
- なるべく,ハラスメントが発生した日時・内容等について記録を残しましょう。
学内における相談体制
- 帯広畜産大学は,ハラスメントの相談先として学生相談室,ハラスメント相談員及びハラスメント審査委員会を設置しています。
- 学生相談室は,学生からのハラスメント相談のほか学生生活上の様々な悩みに関する相談に応じています。ハラスメント相談員は本学構成員及び関係者のハラスメント相談に応じています。ハラスメント審査委員会はハラスメント被害の申立てを受け付けて事実関係の調査を行う組織であり,学生・教職員からの相談にも応じます。
- 上記相談先の教職員には守秘義務がありますので,安心して相談してください。
相談窓口の連絡先
学生相談室
以下のサイトをご覧ください
https://www.obihiro.ac.jp/navi-student-counseling-room
ハラスメント相談員( R6 .4. 1~ R8. 3. 31)
| 役職 | 氏名 | 内線 |
|---|---|---|
| 人間科学研究部門教授 | 平舘 善明 | 5597 |
| 獣医学研究部門教授 | 室井 喜景 | 5365 |
| カウンセラー | 守谷 恭輔 | 5638 |
| カウンセラー | 横山 真澄 | 5638 |
| 研究支援課長 | 長谷川 祐希 | 5346 |
| 保健管理センター看護師 | 村山 由紀子 | 5793 |
ハラスメント審査委員会
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 副学長 | 古林 与志安 |
| 副学長 | 仙北谷 康 |
| 副学長 | 中野 昌明 |
| 学長補佐 |
川島 千帆 |
|
ハラスメント審査委員会連絡先 帯広畜産大学企画総務課長又は企画総務課課長補佐 電話:0155-49-5213 又は 0155-49-5214 メール:harassment@obihiro.ac.jp |
|