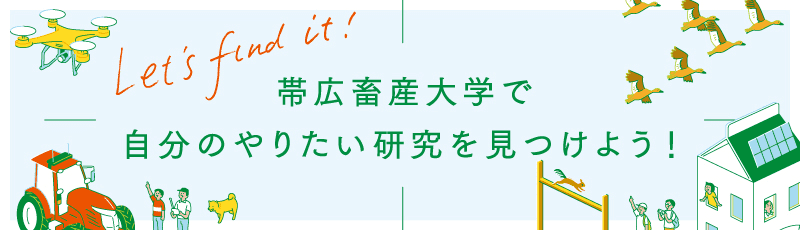第73回畜産学部学位記授与式、第64回別科修了証書授与式、第57回大学院学位記授与式が、3月19日(水)午前10時から講堂において、挙行されました。
今年度の卒業生は学部卒業生224名及び博士前期課程修了生56名に学位記が、別科修了生に修了証書がそれぞれ代表者に授与されました。また、博士後期課程修了生5名、博士課程修了生1名にそれぞれ学位記が授与されました。
次いで長澤学長から告辞が述べられたのち、北海道国立大学機構の長谷山彰理事長による祝辞映像が放映されました。来賓祝辞では、ご臨席いただいた帯広畜産大学同窓会会長の三津原勝様からお祝いの言葉をいただきました。
その後、卒業生を代表して畜産学部畜産科学課程の喜羽夏未さんによる答辞がありました。
続いて学生表彰があり、学業成績優秀者8名に表彰状の授与並びに学生後援会から記念品の贈呈が行われました。
最後に、来賓・教職員紹介があった後、マンドリンサークルによる帯広畜産大学逍遥歌が演奏され、卒業生、修了生が退場し、式が終了しました。






告辞
本日ここに、関係各位のご臨席をいただき、令和6年度の学位記並びに修了証書授与式を挙行できますことは、本学にとりまして大きな喜びです。
それぞれの課程を修了され、本日、この式典に臨むことができますのは、皆さん自身が努力と研鑽を重ね、それぞれの課題を克服した結果です。
留学生の方々は、環境や文化の違う地において、さらに苦労が多かったと思います。卒業あるいは修了の時を迎えられた304人、すべての皆さんに、心からお祝いを申し上げます。
また、ご家族の皆様には、感慨もひとしおのことと推察いたします。誠におめでとうございます。
さて、本学は、我が国で初の官立高等獣医学校として、昭和16年(1941年)に創設され、今年で84年目を迎えます。
第一回卒業証書授与式は昭和18年(1943年)9月に挙行され、104人の一期生が本学を巣立ちました。当時は、太平洋戦争の真っただ中であり、多くは、陸軍などに進んでいきました。卒業後に迎える社会の状況には、不安がいっぱいだったことが予想されます。
終戦後の昭和24年(1949年)には、国立大学設置法が公布され、施設・設備が十分ではない中で、新制大学として帯広畜産大学がスタートしました。初代学長の宮脇冨先生は、「農学を有機的ならしめ、我が国の農業を革新的に発展させる。」と宣言されました。
新制大学がスタートしてから76年が経過した現在、学内の教育研究環境は格段と整備が進み、宮脇先生の宣言通り、農業は革新的に発展しました。これまで本学を巣立った、1万9千275人の同窓生は、農学を有機的に発展させてきました。
農学の歴史は古く、人類の歴史とともに歩んできたと言っても過言ではありません。当初、農学は人類の生活の糧を担う学問でしたが、現在では、食料生産だけではなく、食品の加工や流通、食の安全安心といった分野も対象としています。
また、農学は食料や資源として生物を扱うことから、生命に関わる基礎科学も重要な要素となります。さらに、生物と環境が対象となることから、環境問題においても、その解決には農学の知識と実践力が必要となっています。
農学は、生産農学、畜産学、獣医学、農芸化学、農業経済学、農業工学、森林学、水産学など、食料や生活資材、生命、環境を対象とし、自然と社会すべてに関わる総合科学です。
今日、私たちを取り巻く環境は、誠に厳しいものがあります。本年2月4日に帯広では、観測史上最大となる一晩で124cmの積雪がありました。気候変動にともなう自然災害は、世界中で、後を絶ちません。また、人口問題に関して、日本では少子高齢化による生産人口の減少や地方創生が課題となる一方で、世界の人口は増加し続けています。人口の増加に伴い、エネルギーや食糧が必要となります。その結果、森林の減少、砂漠化が進み、環境破壊が問題となっています。
これらの社会課題の解決には、本学の専門分野である、農学、畜産科学、獣医学分野を含む、異分野を統合した有機的な取り組みが必要であり、あらためて、本学が掲げる「食を支え、くらしを守る人材の育成」の重要性が認識されるところです。
本学のミッションは、「知の創造と実践によって実学の学風を発展させ、『食を支え、くらしを守る』人材の育成を通じて、地域及び国際社会に貢献すること」であり、本学の人材育成目標は、食と農の大切さ、動植物の命の尊さを心得た素養を基礎として、いわゆる「Farm to Table」の幅広い領域を学際的視点で捉える能力と、あらゆる現場に適応できる知識・実践力を有するとともに、地球規模課題解決等の国際的視野を備えたグローバル人材を育成することです。
本日、卒業あるいは修了を迎えた皆さんは、本学がミッションに掲げたグローバル人材として、現在の社会課題に挑戦し、解決に向けて、道を切り開くものと確信しています。今後、想定外の事柄や、困難な課題に遭遇した時は、「農学を有機的ならしめ、農業を革新的に発展させた」先輩たちを思い出してください。
決して、物事をあきらめず、新しいことに挑戦し、自らのアイディアと努力で、困難な課題や想定外の局面などに真っ向から立ち向かい、将来の担い手となって社会を牽引してください。
最後に、「食を支え、くらしを守る」人材として、皆様が、「Farm to Table」の様々な分野において大いに活躍し、地域社会や国際社会に貢献することを祈念して、告辞といたします。
令和7年3月19日
帯広畜産大学長
長澤 秀行