3月8日(金)小樽商科大学 札幌サテライトにおいて,2023年度 HACCP・食品安全管理プログラム 第8回研修「札幌セミナー」を3名の講師を招いて開催し,会場とオンライン合わせて46名が参加しました。
始めに,帯広畜産大学の通山志保客員教授から「最近の食品安全情報」と題して,本年1月に厚生労働省から発表されたリコール・自主回収情報や菓子に関する食品事故事案,さらに食品事故防止について説明がありました。
通山氏は講演の中で,食品事故を減らすキーワードは人の「行動」ですが,従業員は教育訓練を受けて知識があるだけではダメで,知識・能力を行動に変えて,期待される結果が出せる力量のある人を育てることが大切であること。また,管理者(トップ)は,成果を実現できる環境を整え,従業員の教育と理解度を把握して,食品安全は全体で取り組むことが必要と述べました。

会場の様子 司会は三宅俊輔准教授(帯広畜産大学)
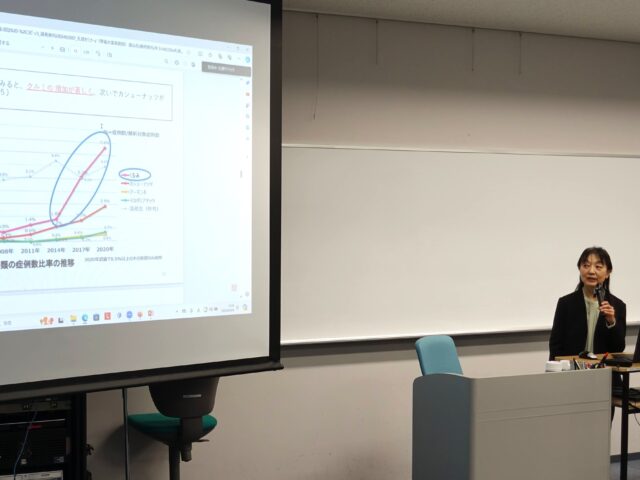
講演1 講師の通山志保客員教授(帯広畜産大学)
続いて,石屋製菓株式会社取締役の柳澤和宏氏から「HACCPシステムの事例紹介 石屋製菓における人材育成」と題して,食品製造業としてどのような考えで人材育成を行っているかについて紹介していただきました。
石屋製菓では『最後は人!』という考え方を重視しており,機械化,システム化が進んでもそれを取り扱うのは人であり,人がやるとどうしてもミスをすることから,製品の監視装置等,人以外の部分に投資をして,人の負担,精神的重圧を減らしていること。また,「正しい管理ができる人(品質管理の知識を持ち,無理をしておらず,改善意欲をわかせて,やったことが認められる人)」の環境を整えることが経営者の役割と説明しました。
柳澤氏がモットーにしている「心技体」について,心:まずは人の心が満たされていることが大事であり,技:技は知識,知識も絶対に大事で,知識がないと知恵を働かせることができない,体:最後は人間,体が基本なので健康でいつも業務にあたっており,何か得るものがあれば皆に話すことを心がけているとも述べられました。
最後に,日糧製パン株式会社参与の沖 昇平氏からは「食品衛生管理のヒヤリハット事例~食品工場の現場から」と題して,自社の食品製造現場で起きた失敗事例をもとに,危害分析の重要性について説明されました。
食品産業を取り巻く様々なことやもの(技術,機械,機具)が高度化,複雑化,専門化しているなかで,一企業の限られた担当者ではその知識や情報を取得・把握しきれないことから,相談できる人や機関を広く多く持つことが大切であること。現場では想定や想像を超えるようなことも起きるので,このような研修等の機会を通じて,相談できる人や仲間を作りたいと述べられました。

講演2 講師の柳澤和宏氏(石屋製菓株式会社取締役)

講演3 講師の沖 昇平氏(日糧製パン株式会社参与)
受講者から寄せられた感想の一部を紹介します。
・実際に企業の最前線で活躍されている講師の方のお話が聞けて大変ためになりました。
・最近の食品安全情報について,食品関連事業者から相談を受ける機会があるため,より適切に伝えることができるようになったと思います。
・帳簿関係のDX化を進めている最中でしたので大変参考になりました。また,危害要因分析の重要さをあらためて認識しました。
・金属探知機の性能や食品衛生は『人が重要である』ことを部内でも伝達したいと思います。
・食品安全情報や他企業のヒヤリハット等自社へフィードバックし,活かせると思いました。
本学では,次年度以降もHACCPシステム導入や従業員のHACCP教育を検討されている事業所等の支援となるよう研修を継続していきます。
