日本語情報
基本情報
氏名
河津 信一郎氏名よみがな(教員一覧並び順決定時のみ利用)
かわずしんいちろう職階
教授学位
博士(獣医学)資格
獣医師学歴・職歴
1986年 3月 (最終学歴)北里大学大学院 獣医学研究科(修士)1986年 4月 農林水産省 家畜衛生試験場 寄生虫病研究室 研究官
1993年 3月 博士(獣医学)北海道大学
1998年 10月 厚生労働省 国立国際医療センター 研究所 適正技術開発研究室 室長
2006年 8月 帯広畜産大学 原虫病研究センター 先端予防治療学分野 教授
2007年 4月 岐阜大学連合大学院連合獣医学研究科 教授
自己紹介
臨床志望でしたが、気付いたら基礎研究をしていました。基礎研究では直ぐには目に見える成果はでませんが、病気を治そうとする気持ちは臨床家のそれと同じです。
写真1

写真2

備考
連絡先
電話番号
0155-49-5846FAX番号
0155-49-5643メールアドレス
skawazu@obihiro.ac.jp居室
居室のある建物
原虫病研究センター部屋番号
104号室部屋番号をウェブサイトに掲載希望
はい学部(ユニット)
所属ユニット
獣医学ユニット大学院(専攻・コース)
所属専攻・コース(その1)
獣医学専攻所属専攻・コース(その2)
畜産科学専攻/動物医科学コース所属・担当
所属(その1)
原虫病研究センター/国際連携協力部門/国際協力分野所属(その2)
動物医療センター/診断検査科所属(その3)
グローバルアグロメディシン研究センター/獣医学研究部門リンク
研究室(名称)
研究室(ウェブサイトURL)
Researchmap
https://researchmap.jp/sik/研究業績・特許(J-GLOBAL)
その他のリンク(その1)
研究シーズ : https://www.obihiro.ac.jp/facility/crcenter/seeds/295その他のリンク(その2)
帯広畜産大学で自分のやりたい研究を見つけよう! : https://www.obihiro.ac.jp/find-research/category/technology研究紹介
My Dream
寄生虫の不思議を「目に見える」形で明らかにする研究テーマ
「寄生虫ライフサイクルのライブイメージング研究」「現地に即した簡易診断法の開発研究」研究分野
寄生虫学, 獣医寄生虫学, 熱帯医学キーワード
タイレリア, バベシア, 住血吸虫, マラリア原虫, 寄生虫研究紹介
- マラリア
マラリア原虫細胞での、酸化ストレス応答とレドックス(酸化・還元)シグナル、カルシウムシグナルに着目しています。生物は細胞内の酸化・還元バランスやカルシウム振動を利用して、様々な生理機能を調節しています。この仕組みやそこに働く分子の役割を「細胞を観ること」「イメージング実験」に重点を置いて調べています。 - バベシア
バベシアでの遺伝子操作技術の開発を行っています。これまでに、外来遺伝子発現系(各種プローブやセンサータンパク質発現原虫)や遺伝子ノックアウト系を開発し、同原虫の赤血球侵入機構や赤血球内あるいはマダニ体内での発育機構および、重症(脳)バベシア症の病態形成機序をライブイメージングによって「目に見える」形で明らかにしていこうとしています。 - 日本住血吸虫
日本住血吸虫症は、アジア諸国の農村で流行し、農村の保健衛生および家畜衛生と密接に関連した人獣共通感染症です。フィリピンの日本住血吸虫症流行地で、集団遺伝学の手法を用いて、医学・獣医学合同でのOne-Healthアプローチの疫学調査を行っています。また、同感染症の排除に向けて、ヒトおよび動物での感染を正確にモニタリングする、ELISAやPOCTの開発など現地に即した診断法の開発研究も行っています。
研究紹介画像
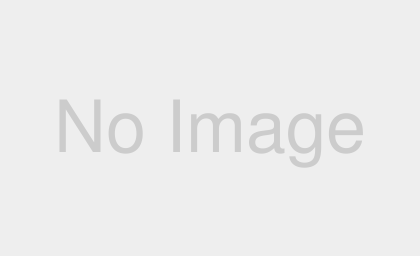
【改良後】現在取り組んでいる研究テーマ一覧
- バベシアライフサイクルのライブイメージング研究
- 住血吸虫症の現地に即した簡易診断法の開発研究
【改良前】現在取り組んでいる研究テーマ一覧
- バベシアライフサイクルのライブイメージング研究
- 住血吸虫症の現地に即した簡易診断法の開発研究
関連産業分野
所属学会
Editor
Editorial Board
プロジェクト
学部生向け
卒業研究として指導可能なテーマ
メッセージ
スペシャルコンテンツ「ぎゅ牛〜っとちくだい」
スペシャルコンテンツ「畜大人インタビュー」
英語情報
基本情報
氏名
KAWAZU Shin-ichiro職階
Professor学位
DVM, PhD資格
DVM学歴・職歴
Graduated from Kitasato University, School of Veterinary Medicine in 1986 with DVM.Received PhD degree in Veterinary Medicine on classification of benign Theileria species in cattle from Hokkaido University in 1993.
Professor of Advanced Preventive Medicine in the National Research Center for Protozoan Diseases at Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicinein 2006.
自己紹介
I wanted to be a clinicions.Basic sceience however can contribute to pathients though it may take longer time.
備考
居室
居室のある建物
National Research Center for Protozoan Diseases部屋番号
Room 104部屋番号をウェブサイトに掲載希望
Yes学部(ユニット)
所属ユニット
Veterinary Medicine Program大学院(専攻・コース)
所属専攻・コース(その1)
Doctoral Program of Veterinary Science所属専攻・コース(その2)
Doctoral and Master's Program of Animal Science and Agriculture/Veterinary Life Science所属・担当
所属(その1)
National Research Center for Protozoan Diseases/Department of Global Cooperation/International Cooperation Unit所属(その2)
Veterinary Medical Center/Diagnostic Resouce所属(その3)
Research Center for Global Agromedicine/Department of Veterinary Medicineリンク
研究室(名称)
研究室(ウェブサイトURL)
Researchmap
研究業績・特許(J-GLOBAL)
研究紹介
My Dream
Imaging amazing parasites lifecycle研究テーマ
“Investigation on lifecycle of babesia parasites using bioimaging analysis”“Development of reliable diagnostics for Schistosoma japonicum infection”研究分野
Parasitology, Veterinary Parasitology, Tropical Medicineキーワード
Teileria, Babesia, Schistosoma, Mararia parasite, Parasite研究紹介
- Malaria
We focus on oxidative stress responses, redox (oxidation/reduction) signals, and calcium signals in malaria protozoan cells. Living organisms adjust various physiological functions by altering the oxidation-reduction balance and calcium oscillation. We focus on “watching cells” and “imaging experiments” to understand the said systems and the roles of molecules that function in the systems, using malaria protozoa as a model organism. - Babesia
We are developing technology to manipulate genes using Babesia. So far, we have developed a foreign gene expression system (green fluorescent protein-expressing protozoa) and a gene knockout system, and we are currently trying to use live imaging to clarify the mechanism of the said protozoa’s growth and infection into the red cells and the vector tick; and the pathology of cerebral babesiosis. - Japanese bilharziasis
Japanese bilharziasis is a zoonotic disease closely related to public and animal health in rural areas of Asian countries. We are developing ELISA and POCT as suitable and affordable diagnostic tools, and are conducting comprehensive epidemiological surveys with the newly developed ELISA protocol and population genetic tools towards elimination of the disease in the Philippines.
研究紹介画像
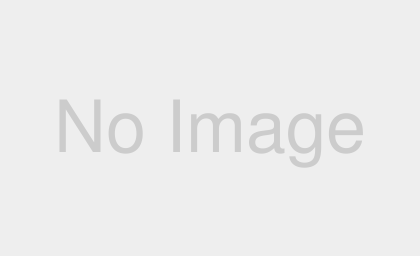
現在取り組んでいる研究テーマ一覧
- Investigation on intra-erythrocytic and ticl-stage developments of babesia parasites using bioimaging analysis
- Development of a reliable and sensitive diagnostics for Schistosoma japonicum infection in humans and animals
関連産業分野
所属学会
Editor
Editorial Board