フードバレーとかち人材育成事業の取り組みの一環として,農畜産業に関わる最新の話題を提供し,関係者の意識向上を目的とした特別講習「農業関連セミナー」を,全3回にわたり開催しました。
11月5日(火)は,「ドローンとAIによる放牧地の管理」と題して,本学環境農学研究部門 川村健介准教授を講師に,20名が受講しました。
始めに,リモートセンシング及びAI技術の基礎知識と活用方法について概要を説明しました。次に,ドローンで撮影した放牧地の画像をAI技術で解析し,放牧管理に活用する方法を,十勝で行われている事例を交えて紹介しました。さらに,講師が現在研究している小型ドローンを使用した牛糞検出技術の開発も紹介しました。
最後に,「生産現場での生産性向上を目的とした精密放牧をよりスマートに実施するためには,プランニングや評価の部分にICTやAI等を駆使し,生産から消費までのバリューチェーンを含めた包括的な取り組みへ発展させる必要がある。」と述べました。

講師の川村准教授

セミナーの様子
11月13日(水)は,「『循環型農畜産業』メタン発生の抑制・未利用資源の利用」と題して,本学生命・食料科学研究部門 西田武弘教授を講師に,13名が受講しました。
始めに,家畜飼料の種類や輸入量,自給率の推移等を説明し,食品製造過程で発生する副産物や規格外の農産物等を有効活用して製造されるリサイクル飼料(エコフィード)の説明をしました。次に,牛や羊など反芻動物のげっぷに含まれるメタンは地球温暖化に与える影響が大きいとされており,飼料によって排出されるメタン量が変わると説明し,メタンを減らす効果のある微生物の「ユーグレナ」や,「カギケノリ」という海藻を利用した飼料の研究を紹介しました。
最後に,COP26で世界全体のメタン排出量を2030年までに2020年比で少なくとも30%減らす目標が発足されていることにも触れ「メタンを抑える開発等を急いで進めていく必要がある。」と強調しました。
受講生からは,「栄養学や分野に通じていなくても理解がしやすい解説と,写真・動画の資料が多く,この分野の展開に関心を持つことができました。」などの感想が寄せられました。

講師の西田教授
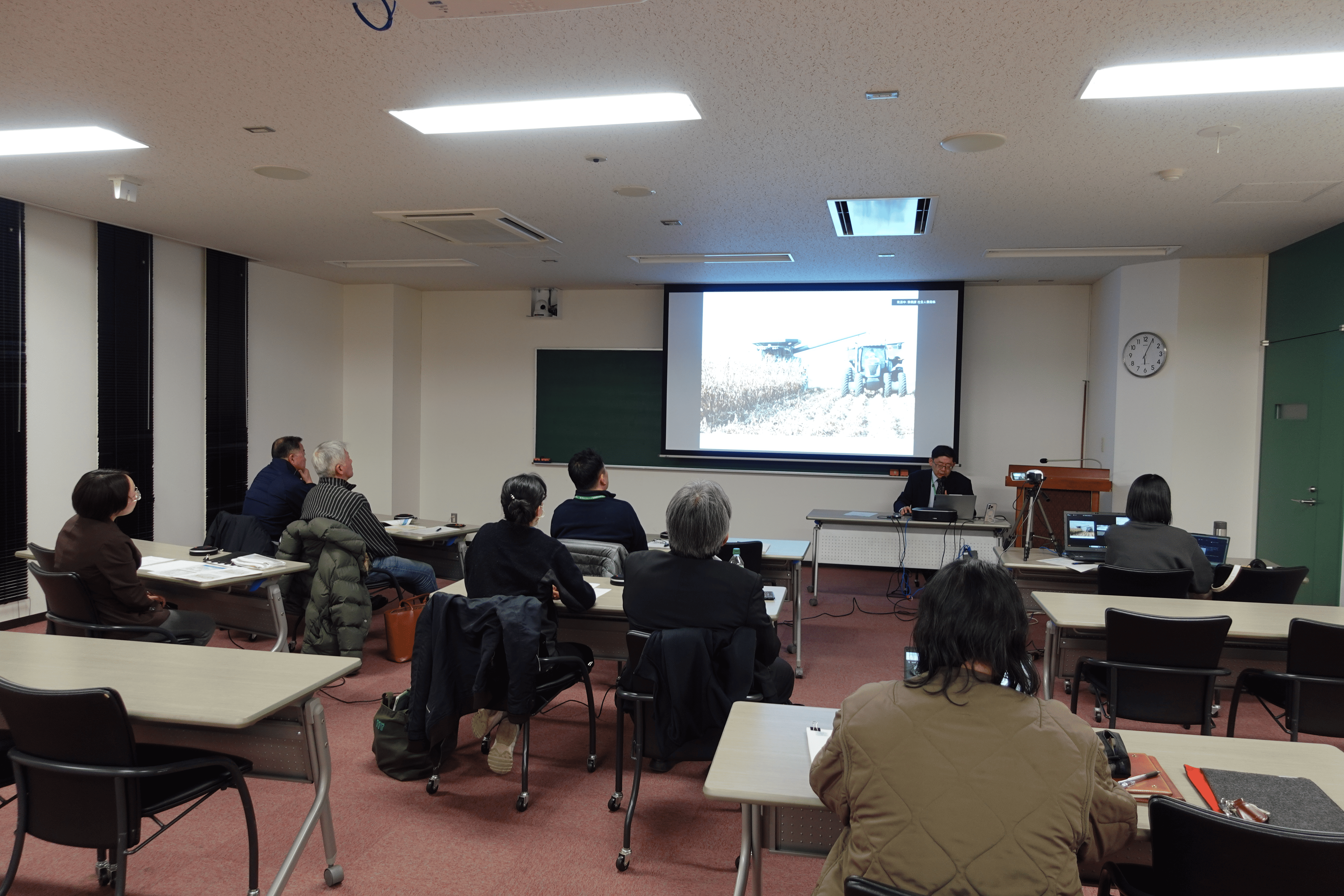
セミナーの様子
11月22日(金)は,「十勝で活きるロボット農機の使い方とその開発現場」と題して,本学環境農学研究部門 藤本与助教を講師に,10名が受講しました。
始めに,十勝は耕地面積が広く年々減少する農家戸数に加え,農業者の高齢化が進むことによる労働力不足が懸念されており,さらに農産物の収穫増加や品質向上のため,より精度の高いロボットトラクタ(ロボトラ)が必要と述べたうえで,十勝で活用できる機能が開発されつつあるが農家への浸透が進んでおらず,使い方が十分に理解されていないロボットトラクタの現状について,なぜ使いづらいのかどこを改善したら使っていけるのか課題を整理しながら説明しました。
続いて,大学で実施したバレイショの耕起作業から収穫まで無人で行うプロジェクトの概要や,実証実験中の農薬を撒く無人防除システムの開発について紹介しました。
受講者からは,「ロボトラで『できること』『できないこと』が学べた点が良かった。」,「ロボトラは,ほ場の大区画化と併せて話題に出る内容であり,現状を知るのに良い機会であった。」などの感想が寄せられました。

講師の藤本助教

セミナーの様子
